自社の有機野菜や平飼い卵、お米を使ったお弁当事業に挑戦(ユアフィールドつくば)
ノウフク・アワード2023で優秀賞を受賞したユアフィールドつくばは、筑波山を臨む茨城県つくば市のNPO法人です。2011年に発足し、今年で13年目を迎え、障がいのあるスタッフ約100名と、それを支える職員約90名が農作業に取り組んでいます。

ノウフク・アワード2023で優秀賞を受賞したユアフィールドつくばは、筑波山を臨む茨城県つくば市のNPO法人です。2011年に発足し、今年で13年目を迎え、障がいのあるスタッフ約100名と、それを支える職員約90名が農作業に取り組んでいます。

近代化で失われた農村の包摂力 我が国はわずか100年前、国民のほとんどが農業に関わる農業国でした。その頃の農業農村は、職業としての経済活動に留まらず、生活の場であるとともに、教育の場でもあり、社会性を育てる場でもありました。

長野県松川町が、株式会社ウィズファーム(長野県松川町)が生産したノウフクJAS認証小麦を1キロあたり800円で購入。町内のすべての小中学校の給食でノウフク小麦を原材料として使用したソフトフランスが提供されました。
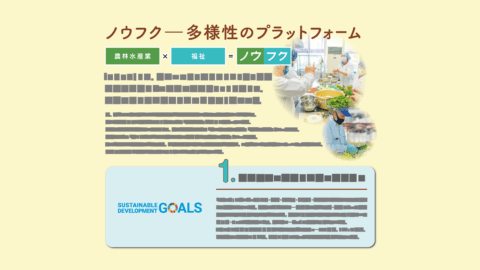
2021年度にノウフク・ラボで制作した「ノウフク営業ツール」を2024年度版に更新しました。全国の農福連携を実践される皆様が、地域の飲食店や小売店、卸売業者などの企業からの理解促進を図るツールとして制作されたものです。

一般社団法人日本基金は、無償の「ノウフクJASに関する説明会」をオンライン(原則Zoom)で開催しています。随時開催していますので、お気軽にお問い合わせください。

6月5日(水)、首相官邸で第3回農福連携等推進会議が開催され、「農福連携等推進ビジョン(2024改訂版)」が決定されました。農福連携等推進会議は、全国的な機運の醸成を図り、今後強力に推進する方策を検討するため、省庁横断の会議として設置。

佐賀県で農福連携のマッチング件数が躍進し、コーディネーター設置から2年目となる2023年度はのべ70件にのぼりました。その立役者の一人が、佐賀県農業経営課 農福連携コーディネーターの藤戸小百合さん。

トヨタ自動車株式会社や専門家、福祉団体などで構成される「地域のトイレ課題解消のための事業投資型モデル実装を目指す会」は、2月20日(火)に都内で「第1回全国コンソーシアム」(トヨタモビリティ基金を活用)を開催しました。

一般社団法人日本農福連携協会の会員事業所が、5月4日(土)〜6日(祝)に開催されたイベント「GINZA SKY WALK 2024」に「日本農福連携協会マルシェ(大丸有SDGs

道では農林水産省の事業を活用し、全国に先がけ農業現場に農福連携技術支援者(農林水産省認定)を派遣しました。第1回目の4月22日は旭川市の農場において、農業者、福祉事業所職員、福祉事業所利用者(障がい者)の3者に農作業現場での農福連携に関する指導・助言を行いました。